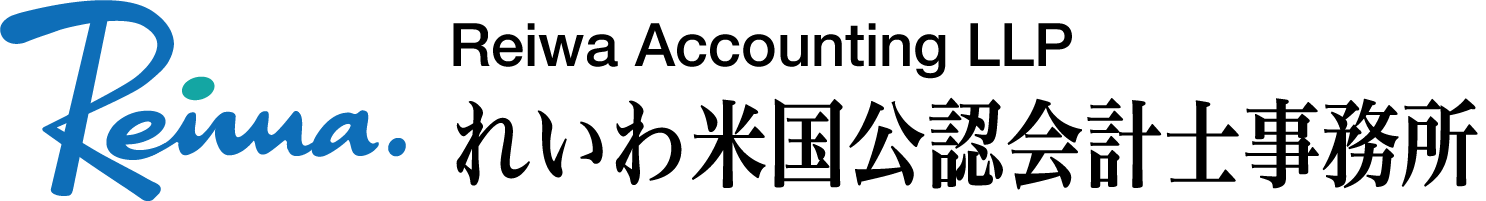前回小欄にて、筆者が、IRS指針の執筆担当官僚から直接聴取を行っている事に言及したところ、「そこまでやっているとは、思わなかった」、「どうして、そういった官僚とコンタクトが取れるのか」等のコメントを貰った。 コンタクトを取るのは簡単だ。IRSが発行する財務省規則草案のPreamble、最終規則のTD、またその他指針の多くには、執筆者、担当者の名前、コンタクト番号が記載されているので、規則、指針の内容に不明な点があれば、その者に電話する。ただ、電話しても、電話を取ってくれる事は殆ど皆無だ(私の経験では、1度も取って貰った事は無い)。ボイスメールに、質問の内容を要領よく伝え、Call backを待つ。大体2,3日中にCall backをくれる。彼らはIRS内のOffice of Chief Counsel、Office of Associate Chief Counselに所属しており、弁護士である者とそうで無い者がいる。弁護士ライセンスが無くても、この国の財務省規則、指針を執筆している人も居るという事だ。 規則や指針の実際の執筆者に質問するのだから、何でも答えられるだろうと思いがちだが、そうではない。こちらも、重箱の隅をつつくような質問ばかりするからだ。これまで、即答頂けた事は殆どない。「同僚と確認したうえで、回答するので、数日~数週間待ってくれ」也の対応が多い。部署内で確認した回答を頂いても、またそれに対して追加質問をする場合もあるので、ケースによっては何度もやり取りを交わす。そのうち、直通電話を教えてくれる人も居る。 日本で勤務していた時代に、審理事務担当に連絡しアドバイスを仰いでいたが、審理に相談した経験のある読者ならば、国は違えど、税務の実務家と官僚とで如何なる対話が交わされるか、容易に想像がつくと思う。我々会計事務所は情報サービスであるが為、常に信ぴょう性の高い”ネタ”を追っているという点では、メディアに似ている。その為、出版社のエディター、弁護士、コンサルタントらとのつながりが重要なのだが、規則や指針を執筆している官僚から得る知見は、何ものにも代えがたいものだと思う。 官僚との接触を通じ、思いがけない経験をした事がある。Stepped-up basis(内国歳入法1014(f)条)に関する財務省規則草案が発表された直後、「日本の居住者が米国資産を遺して亡くなった場合で、相続税条約上の恩典を使えば米国エステートタックスが生じないはずなのに、諸々の理由にてエステートタックス申告書&条約開示(=Forms 706NA & 8833)が未提出だった場合、当該米国資産についてはStepped-up basisが適用できるのか否か」尋ねたところ、「そうしたシナリオについて、財務省規則草案は想定していないので、答えは無い。最終規則を作る過程で参考にするので、連邦政府宛てにコメントを提出してくれ」と頼まれた。 依頼を受けRegulations.govに以下の趣旨のコメントを提出した。 A comparative reading of Prop. Regs. 1.1014-10(b) and 1.1014-10(c)(3)(ii) points that the consistent basis requirement does not apply to any property that is includible in the decedent's gross estate from which no tax arises regardless whether the filing requirement under IRC Sec 6018 with respect to the decedent's estate has been met. In the case of a noncitizen nonresident decedent's estate, the estate is subject to the IRC Sec 6018 filing requirement if such part of the gross estate as…
Read More
TCJAの下、内国歳入法274条が改正された為、企業が職員の為に負担する交通費、駐車場代につき、損金算入不可能となるケースが増えた。テナントビルの場合で、テナントが駐車場代込みでオフィス賃料を支払っている場合でも、同賃料に含まれる駐車場代相当分につき否認されるケースもある。否認されるケースの多くは、テナントビル駐車スペースの半数以上を自社職員が利用している場合。2020年12月に発表された財務省規則の下では、同一テナントビルの他のテナント職員や客らの駐車が過半数を占める状況においては、駐車場代相当分の損金算入が依然として可能な為、割を食うのは、大口のテナントだ(米国財務省規則1.274-13(b)(3)(ii))。逆に、小口テナントにとっては朗報なのだが、財務省規則の文言が、実務家を悩ませている。 Multi-tenant building. – If a taxpayer owns or leases spaces in a multi-tenant building, the term general public includes employees………clients, or customers of unrelated tenants in the building. 同一ビルのテナント職員や客は、‘一般大衆’と 見なされ、これら‘一般大衆’の駐車が過半数占めるか否かで、損金算入、不算入が決まる。が、この文言では、同一敷地内の複数のテナントビルが駐車場を共用している場合に、ルールが如何に適用されるかわからない。敷地内の他のビルのテナント職員や客までも‘一般大衆’と見なすのか。 LAも一歩郊外に出れば、広い敷地に低層のテナントビルが散在する箇所も多いため、本件多くのクライアントに少なからず影響するが、TD(=最終規則発表時に発行される解説)にも手掛かりはなかった。 結局、財務省規則を実際に執筆したIRS部署(Office of Associate Chief Counsel)に照会したところ、(部署としてではなく)一個人の考えと断った上で、「複数のテナントビルが同一敷地内の駐車場を共用する場合、全てのビルのテナント職員や客を‘一般大衆’と見なす」也の見解を得た。 実務において、財務省規則の執筆担当部署に直接コンタクト取る事は、滅多にないが、最近もう1件照会した事があった。それは、Employee retention credit(ERC)のルール運用においてFull-time employeesの数を勘定する際に、海外での勤労時間数をカウントするか否かという問題であった(内国歳入法3134、4980H)。日系企業にとっては、最重要の事案だが、この点については、「法に鑑み、誠実に対応してくれ」也の回答を得た。筆者も含め、当問題につき思案してきた実務家には、十分な回答であった。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More
今回は、2022年に新リース基準を適用したときの経過措置を見ていきたいと思います。会計基準の変更なので、retrospectiveな遡及適用が原則です。但し、遡及適用は煩雑なので以下のような2つのtransition methodが設けられています。 ASC 842-10-65-1 Retrospectively to each prior reporting period presented in the financial statements with the cumulative effect of initially applying the pending content that links to this paragraph recognized at the beginning of the earliest comparative period presented. Under this transition method, the application date shall be the later of the beginning of the earliest period presented in the financial statements and the commencement date of the lease. Retrospectively at the beginning of the period of adoption through a cumulative-effect adjustment, Under this transition method, the application date shall be the beginning of the reporting period in which…
Read More
新リース基準(ASC 842)での大きな変更点は、lessee側のオペレーティング・リースの扱いです。旧基準(ASC 840)ではコミットメントとしてリース債務がfootnoteで開示されていただけですが、Right of Use Asset(ROU asset)という概念を新設してオンバランス化されることになりました。ROU assetは、an asset that represents a lessee’s right to use an underlying asset for the lease termと定義されており、ファイナンス・リース、オペレーティング・リース双方で使われます。 理論的な面は、後日触れるとして、実際にオペレーティング・リースをオンバランス化するというのは、どういうことか設例を使って見ていきます。 【設例1】 5年のリースで、各年度の終わりにリース料を、5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000と漸増して払っていく。割引率は9%で、この率を基にしたリース総額の現在価値は、55,000である。オペレーティング・リースと判定された。 これをASC 842に沿って表にすると以下になります。 合計 75,000 20,000 55,000 55,000 75,000 年 リース料 利息 相当額 リース 債務減少 リース 債務 ROU asset 償却 相当額 ROU asset リース費用 B/S B/S P/L (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) =(a)-(b) =(g)-(b) 当初残高 55,000 55,000 1 5,000 4,951 49 54,951 10,049 44,951 15,000 2 10,000 4,947 5,053 49,898 10,053…
Read More
新リース基準(ASC 842)の適用時期が近付いてきました。暦年の非公開企業は、2022年末から適用なのですが、期末に財務諸表を作る際に期首に適用を開始した形にする必要があります。今後しばらくリースの論点を取り上げていきます。 概要 まず、リースについては、新収益認識基準でおなじみとなったcontrol概念を使って、 contract that conveys the right to control the use of an identified assetと説明されています。因みに今まではAn agreement conveying the right to use property, plant, or equipmentとされていました。 新リース基準では以下のような区分がされています。 Lessor側 Lessee側 Sales -type - Finance Direct financing - Operating Operating - Operating 旧基準では以下のようになっていました。 Lessor側 Lessee側 Sales -type (Capital) - Capital Direct financing (Capital) - Capital Operating - Operating 今まであったcapital leaseがなくなっていますが、大雑把な理解としてはcapital leaseがsales-type leaseに移行したと捉えて問題ありません。 Sales-type leaseの条件 根底には、新収益認識基準の次のようなcontrol概念ががあります。 Control of an asset refers to the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from the asset リースにおいて資産が売却されたと見做して会計処理するためには、上述したconveys the right to control the use のみならず、substantially all of…
Read More
これは一見簡単そうだが、日米の違いが大きく結構問題になる。 日本の扱い 日本では、企業会計原則が以下のように定めている。 第2-6 特別損益 「特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。」 なお、注解12では、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができると定めている。 アメリカの扱い 一方、USGAAPだが、これはASC (Accounting Standards Codification)360-10-45の固定資産の条項で示されている。 360 Property, Plant, and Equipment 360-10-45 Other Presentation Matters>> Presentation of Disposal Gains or Losses in Continuing Operations 45-5 A gain or loss recognized on the sale of a long-lived asset (disposal group) that is not a discontinued operation shall be included in income from continuing operations before income taxes in the income statement of a business entity. If a subtotal such as income from operations is presented, it shall include the amounts of those gains or losses. 意味するところは、営業利益項目として計上しなさいということである。なお、 If a subtotal such as income from operations is presentedとあるのは、USGAAPでは、営業利益のsubtotalを出さないsingle…
Read More
前身である永野森田会計事務所より分離独立して以来この11月1日で一周年を迎えました。おかげさまで、お客様及び日本の監査法人、税理士法人等からも信頼を賜り順調に事業は伸びてきています。皆様のご支援に厚くお礼申し上げます。 小さな事務所ですが、技術的に高度でかつきめ細かいサービスを提供する事務所でありたいと考えています。皆様のご参考にしていただくため一周年にあたり弊事務所のサービス内容に関しても、他の会計事務所には例がないほど踏み込んだ内容を掲載いたしました。 Covid19で大変な状況ですが、皆様のご無事と更なるご発展を祈念するとともに、今後とも皆様のご支援とご鞭撻を賜るようお願い申し上げます。
Read More
FASBは、コロナウィルス・パンデミックに対応して2020年6月3日にASU No.2020-05を発行し、新収益認識基準(ASC 606)と新リース基準(ASC 842)適用の一年延期を決めました。適用になるのは、非公開企業、非営利企業になります。 新収益認識基準に関しては、2019年12月15日後に始まる事業年度まで適用が延期できます。なお、2020年6月3日現在において適用していない会社が対象になります。このため多くの12月決算の会社は2019年12月期に既に適応済みということになり影響を受けません。 新リース基準に関しては、2020年12月15日後に始まる事業年度から、2021年12月15日後に始まる事業年度に延期されました。 両基準とも任意の早期適用は依然として認められています。
Read More